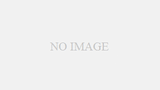こんにちは!借金4000万円医学生maruです!
私いま、絶賛、試験期間でございます。これを書いている今日も昨日も、そして明日も試験です。
大変ですが、普段の100倍くらいの集中力で知識を吸収し、それを答案用紙にぶつけるのも楽しいといえば楽しいです(その分、私生活が崩壊するのでQOLはプラマイゼロですが…)。
今日はそんな医学部の進級試験について、入学当初から思っていたことをここで吐露させていただければと思います。
1/3ルールと留年
医学生なら365日、常に頭の片隅にあるのが、「勉強しなくちゃ」という強迫観念。そして、その根源は「留年」への恐怖心です。
たいてい、世の中の物事には良い面と悪い面が共存しているものです。常に医学では悪者の「酒」や「タバコ」でさえ、嗜む人にとっては、将来の健康を脅かすとはいえ、その瞬間はQOL爆上がりです。大学進学にしても、東大に行こうがFラン大に行こうが、得られるものや失うものはそれぞれの大学であるはずです。
ですが、私立医学部における留年には、なんのメリットもないように思うのは僕だけではないでしょう。だから僕たちは将来の患者さんに還元するためという建前で、留年怖さに必死こいて勉強することができているというのは否めない事実であります。
【留年で失うもの】
(1)1年という時間
(2)約600万円の学費
(3)友達との楽しい学生生活
中には、それでも重い腰が上がらず、勉強のスイッチが入らない“お金持ちかつやる気のないおぼっちゃま&お嬢様がた”がいらっしゃいますが、庶民にはとても真似のできない芸統です。
僕の通う大学では、テストでは60点以上で合格、本試験でそれに満たなかった生徒は、追試験を受験します。それにも受からないと留年確定です。また、授業を1/3以上欠席すると、その科目の試験の受験資格が与えられません。そして、一科目でも合格できない科目があると、留年が確定します。
なので、授業に出て、かつ結果も出さないといけないというわけです。
キミたち馬鹿だから過去問どおりにしてあげる
過去問なしでは進級できない! そう僕は断言できます。
1.5時間の講義(スライド平均100枚)×平均20講義×約15科目=450時間、30000枚分のスライドの知識を、数週間の毎日の試験で試されるわけです。
講義では、毎回違う講師の方が登壇し、素人同然の僕たちは基本的に毎回新しい話を座学で学びます。時々、図が一切ない紙の講義資料を作って来られる先生がたもいます。僕たちは、聞いたことのない専門用語とともに、合っているかわからない自作の図を空想して、そういう先生の説明を脳内補完していきます。
時には、200枚を超えるスライドを用意して、終わらせるために早口言葉で何かを喋って、最後に「ちょっと駆け足でしたが」と、ご自分の使命は果たして満足して帰っていかれる先生もいます。
また時には、「講義の内容は、学生には5%しか定着しないというデータがあるみたいだね」と他人事のように笑って講義を始める先生もいます。確かに、エビングハウスの忘却曲線では、1日後には74%を、1ヶ月後には79%を忘れるそうです。定期的にスライド30,000枚分の知識を復習しないと忘れてしまう、というのが現実です。
生徒からすれば、医学は難しい。何よりカリキュラムが厳しい。それを先生方もわかっていて、試験問題は簡単にする…のではなく、過去問どおりにするというのが8割型の先生のやり方です。これまでの生徒の質を見て、キミたちには毎年違う試験を出しても答えられないでしょ、馬鹿の一つ覚えでもいいから試験だけは通りなさい、ということでこういう策を講じているという説もあるそうです。
悲しいのは、貴重な学生時代のほとんどの時間を使って出席した講義で、知識が身につかないという実態があることです。
臨床現場で見たことは忘れない
座学ではすぐに忘れてしまうことも、実習で見たことは忘れないものです。
僕の学校では、ポリクリ前は99%の時間は座学なので、「Skipper Modelはがん細胞が一定数まで増加すると人間は死ぬ」という概念であるとか、「肺癌の治療方針決定のために実施すべき分子診断はEGFR、RET、MET、BRAF、ALK、ROS1である」とかいう呪文を覚えては忘れて…、ということが繰り返されているわけです。
そして、僕はこのまま臨床現場に出たら、ただのポンコツじゃね?という発想に至りました。
学校のほうで実施してくれる“目で見て医学を学ぶ機会”は、ポリクリ前はほとんどないのです。でも、数少ない病院実習で見聞きしたことは、今でも覚えています。そこで、医学生という身分を利用して、個人的に病院に行けばいいのか!と思いつきました。
先日、優しそうな先生にお願いして、附属病院に潜入してきました。病理の先生だったので、マンツーマンで血球の鑑別の仕方を教えていただいたり、たまたま術中迅速診断の依頼が来たり、臨床検査技師さんがパラフィンに埋め込んだ組織を機械でものすごく薄く削っていたのを手伝わせてもらったり…
またある時は、形成外科で、ネコに噛まれた患者さんの傷の上からメッシュ状にして皮膚移植をしているのを見て、トキソプラズマを思い出して、妊婦が感染すると赤ちゃんに悪影響が出るな、ネコは好きだけど結婚してからしばらくは我慢しようかな、などと知識が体験に基づいて繋がってきます。
先生方の多くは、医学生のほうから求めれば、惜しみなく学修の機会を与えてくれるように感じました。他大学の知人の話を聞くと、低学年のうちからどんどん附属病院をローテートしているとか。でも、カリキュラムって一生徒の考えで動くものでもないしなぁ…。ということで、自分で考えて行動するしかないですね。試験だけ受かって内容が伴わない医学生にならないよう、これからも積極的に臨床現場での学修の機会をゲットしていきたいです!
まとめと次回予告
今回は、僕の通う大学の試験のあり方について書かせていただきました。この記事の読者は現役の医師が多いと思うので、「先生方の時代はこうだった!」という感想などをよかったら聞かせてください(‘ω’)ノ
もうこんな時間! 明日の試験勉強の続きをやらねば(;゜0゜)ということで今日はこの辺で失礼します。
次回は医学部で麻痺していく医師としての倫理観というテーマです。
次回も読んでもらえると嬉しいです!お楽しみに!
下の広告から購入またはご契約していただくと僕に収益が入ります。応援してくださる方は是非よろしくお願いします!お小遣いにさせていただきます(>_<)
<ブログ・SNSはこちら>
・m3.com: https://membersmedia.m3.com/articles/11589#/
・X(旧Twitter)アカウント:https://twitter.com/4000manyen_ms
・Instagramアカウント:https://www.instagram.com/4000manyen_ms/